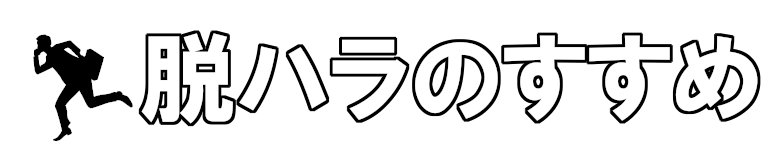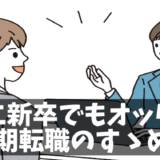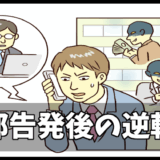この記事は、クラウドワークスで募集した「ハラスメント体験談」の記事を書いてくださった@akane_writer27さん(20代女性)の記事です。
以下、プロフィールです。
ユーザー名:DigitalAsuka28
3年目の派遣社員。
大学卒業後、正社員として出版社に勤務するも1年で退職。
その後、派遣社員として複数の企業を経験し、現在は大手消費財メーカーのマーケティング部でSNSコンテンツ制作を担当。
趣味は韓国ドラマ鑑賞と猫カフェ巡り。
将来はフリーランスのコンテンツクリエイターとして独立することを目指している。
【自己紹介】不安定な立場で働くということ

マーケティング部でデジタルコンテンツを担当している派遣社員です。
甘いものが大好きでジムに通いながらスイーツとの戦いを日々繰り広げ、休日は韓国ドラマを一気見するという、ごく普通のアラサー女子です。
派遣社員として2年目に入り、常に感じるのは雇用の不安定さです。
3〜6ヶ月単位の契約更新がいつも頭から離れず、「次も働けるだろうか」という思いが常につきまといます。
入社当初は認められようと必死になり、常に120%の力で取り組んでいましたが、そんな働き方が長続きしないことにすぐ気づかされました。
日常的なオフィスのイライラ
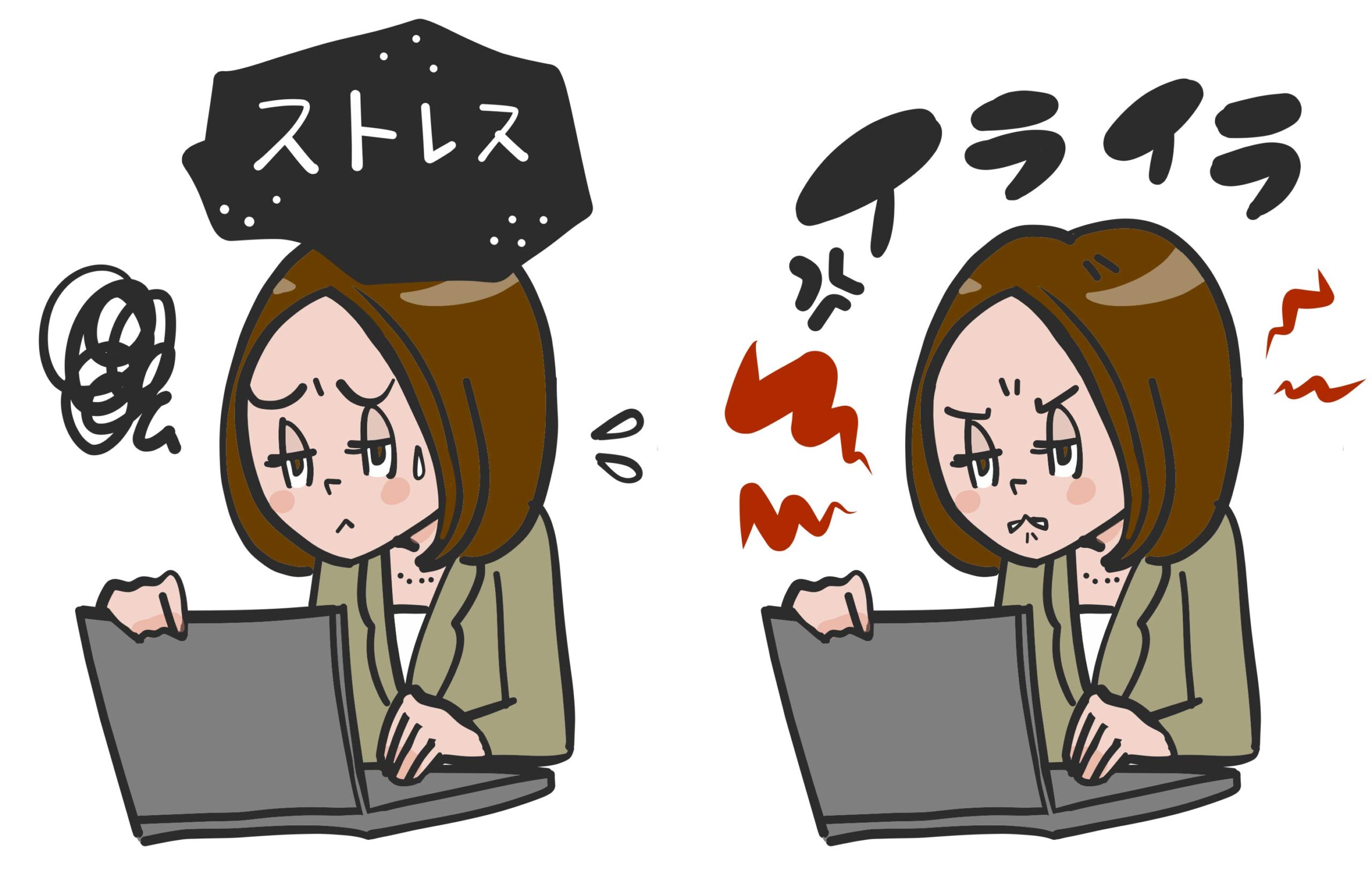
オフィスでの生活には小さなストレスが山積みです。
「環境のため階段を使いましょう」のポスターを見ながらエレベーターを選ぶ後ろめたさ、お湯が切れたポットに直面してカップ麺を麦茶で作る悲しさ、奇妙な食べ方の同僚、温度設定を巡る無言の戦い…。
これらはどれも些細なことですが、毎日積み重なると精神的に疲弊します。
特に非正規雇用の身分では、不満を口にするのも難しいものです。
しかし、私にとって最大のストレス要因は別にありました。
「コロコロ変わる上司の指示」
これこそが私の職場での最大の悩みだったのです。
振り出しに戻される絶望感
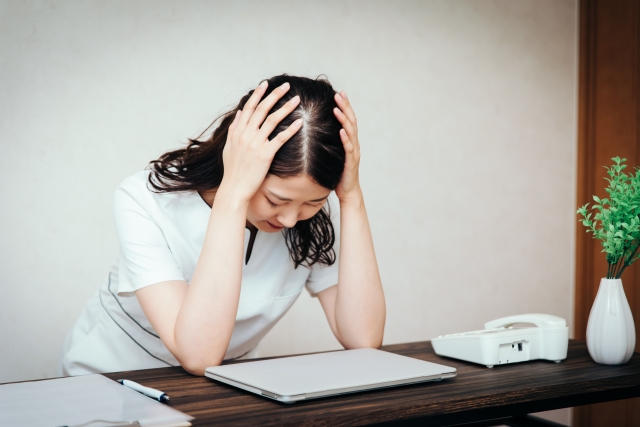
何度も確認しながら作り上げた企画書。
提出したら返ってくるのは「違うなぁ、一からやり直してくれる?」という言葉。
そんな経験が一度や二度ならまだしも、これが常態化すると本当に心が折れそうになります。
先日担当した新商品のSNS発信計画では、最初「若者向けカジュアルトーン」で指示を受け、作成後に「やはりブランドイメージを意識した上品な感じで」と方向転換。
再提出すると「インパクト不足だからもっと直接的なメッセージで」と再び変更…。
このようなパターンを何度も経験するうちに、「どうせ気に入らないだろう」という予感が的中することが増えていきました。
そして予感が当たるたびに感じる無力感は言葉では表せません。
なぜ指示はコロコロ変わるのか
この現象の原因を考察してみました。
- 上司自身が明確なビジョンを持っていない – 漠然としたイメージはあるものの、それを言語化できていない
- 上層部からの異なる指示に振り回されている – 上司も別の人からの指示で動いている可能性
- 決断力や自信の欠如 – 責任を取りたくないための先送り戦略
ある日、先輩の派遣社員に相談したところ「あぁ、それ部長あるある!前からそうなのよ」と言われました。
つまりこれは私だけの問題ではなく、その上司特有の「特性」だったのです。
職場満足度を左右する上司との関係性
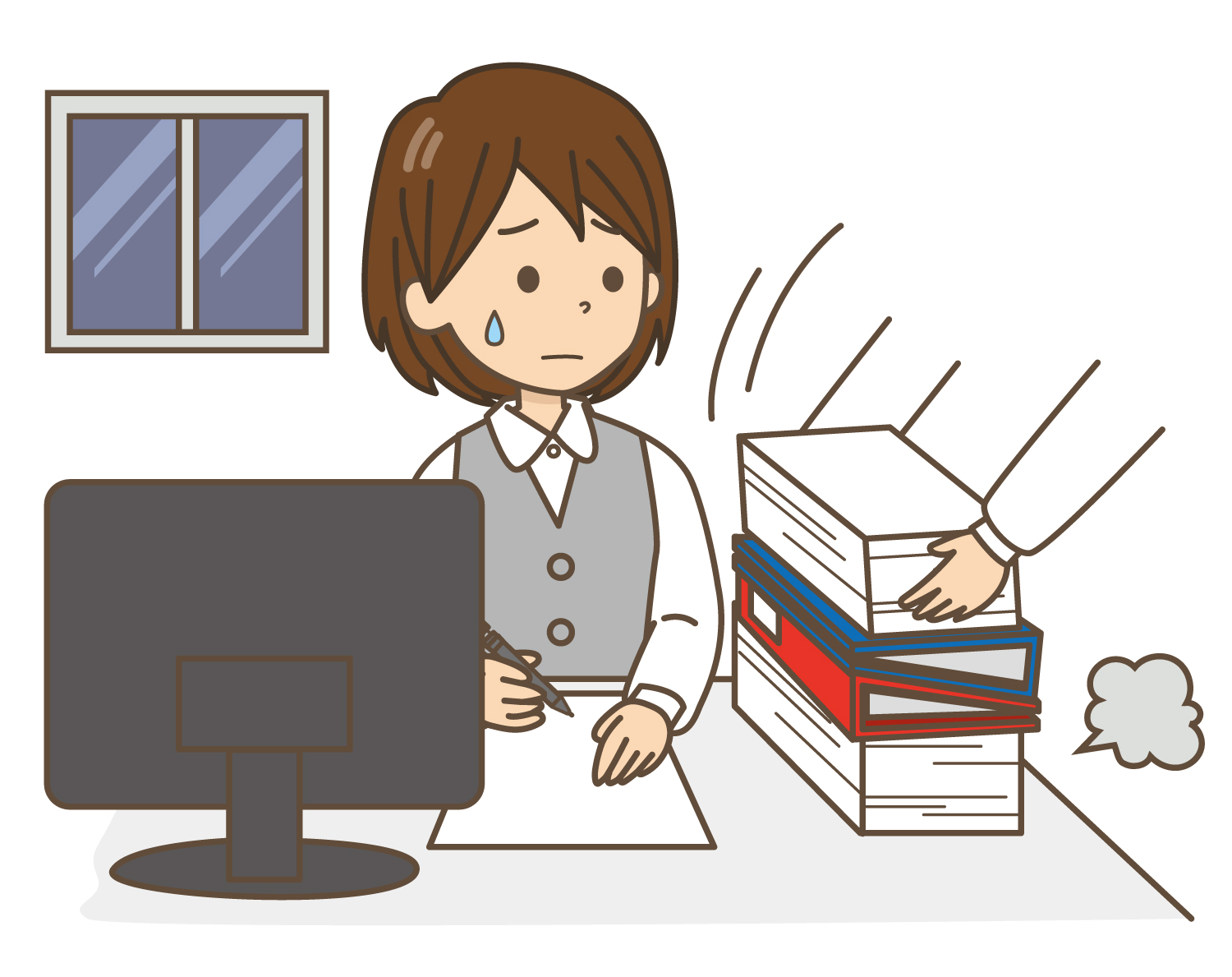
上司との関係が働きやすさを決定づけることを実感しています。
理想的な上司に巡り会える確率は低いものですが、その影響力は計り知れません。
就活中に「会社選びで最も重要なのは直属の上司」とアドバイスされたことがありますが、今ならその意味がよく分かります。
「会社」という抽象的な存在は、実際には具体的な「人」、特に直属の上司によって体現されるからです。
同じ会社内でも、部署によって働きやすさが全く異なるのは、上司の違いによるところが大きいのです。
見つけたサバイバル術→効率的な力の使い方

そんな状況で私が編み出した対処法は、
「修正前提で、エネルギーの半分だけを使って仕上げる」
これは決して「手を抜く」という意味ではありません。
限られた時間と精神力を効率的に配分する戦略です。
仕事の基本的な質は保ちつつも、細部にこだわりすぎない姿勢を意味します。
なぜこの方法が効果的なのか
- 指示が変わりやすい上司は、前回言ったことを覚えていないことが多い
- 完璧を求めて作り上げた資料も、結局は修正になることがほとんど
私の上司は「形になったものを見ないと判断できない」タイプでした。
つまり、言葉での説明より実際の資料を見て初めて本音が出てくるのです。
このような上司に対しては「たたき台」を提供することで、彼らの中のぼんやりしたイメージを具体化する手助けになります。
完璧な資料というより、「思考整理のためのツール」として機能させるのが狙いです。
具体的なアプローチ方法
- まずは骨組みだけの資料を素早く作成する
- 小さな段階ごとに確認を取りながら進める
- 変更指示には素直に従う
- 完成したらすぐに確認してもらう(時間が経つと上司の記憶も薄れるため)
例えば、プレゼン資料なら最初は全体構成とキーメッセージだけを入れた状態で確認。
方向性の承認を得てから詳細を埋めていきます。
その過程でも定期的に確認を取り、「このまま進めて良いですか?」というチェックポイントを設けます。
最終提出時には「修正点があればお知らせください」と一言添えることで、「改善可能な資料」という認識を共有します。
思わぬメリット→生まれる余裕

この方法を実践することで、心に余裕が生まれ、ストレスが軽減しました。
最初は「サボっているような罪悪感」がありましたが、実際には生産性が向上しました。
無駄な労力を省くことで、本当に重要な部分に集中できるようになったためです。
精神的な余裕は上司とのコミュニケーション改善にも繋がりました。
「また変更か…」という不満ではなく「どのような方向性がお望みですか?」と冷静に対応できるようになりました。
時間的余裕も生まれ、深夜までの残業が減少。
ワークライフバランスが改善され、プライベートの充実も実現しました。
これは期待値の適切なコントロールであり、自分と上司双方のストレスを軽減する方法とも言えます。
非正規雇用者としての心構え

派遣社員として避けられない現実は「永続的な安定はない」ということ。
どんなに頑張っても契約終了の可能性は常にあります。
しかし、その不安定さと向き合いながらも日々の仕事に意味を見出すことは可能です。
「この経験が将来のキャリアにどう活きるか」を考えることで、どんな状況でも学びを得られます。
非正規雇用ならではのメリットもあります。
責任の軽さや様々な職場経験の機会など、これらを活かしながら自分なりのキャリアを模索することも大切です。
同じ立場の仲間との横のつながりも重要です。
情報交換や励まし合いが大きな心の支えになります。
自分自身を大切にする方法

気まぐれな指示に振り回される日々でも、自分自身をケアすることが重要です。
- 仕事とプライベートの境界線を明確に(帰宅後の業務メール確認を避ける等)
- 小さな達成感を大切にする(日々のタスク完了も自分を褒める機会に)
- 職場以外の人間関係を育む(家族や友人との時間で仕事ストレスを相対化)
- 身体的なケア(適度な運動、バランスの良い食事、十分な睡眠)
【おわりに】持続可能な働き方を目指して

日々のストレスを軽減し、職場での時間を少しでも快適にするコツは「完璧を求めず、適度な力配分で臨む」こと。
これが上司の気まぐれに振り回されず、自分の心を守る方法です。
この考え方は仕事だけでなく、人間関係や自己啓発など様々な場面で応用できます。
常に全力投球することは短期的には成果を生むかもしれませんが、長期的には持続可能なペースで取り組む方が
結果的に大きな成果につながります。
これからも様々な困難に直面することがあるでしょうが、この「エネルギー配分の哲学」を胸に、柔軟かつ粘り強く歩んでいきたいと思います。
皆さんも、自分なりの「心の安定」を保つコツを見つけられることを願っています。
「職場の言う事がコロコロ変わる人の対処法を上司との実体験を交えて解説」感想

この記事は、多くの非正規雇用者が日々直面している課題に対する実践的な解決策を提示していると感じます。
共感した点
特に共感したのは、「コロコロ変わる上司の指示」への対処法。
この問題は非正規雇用に限らず、多くの職場で見られる現象ではないでしょうか。
筆者が提案する「修正前提で、エネルギーの半分だけを使って仕上げる」という方法は、単なる「手抜き」ではなく、限られたリソースを効率的に活用するための賢明な戦略だと思いました。
また、上司との関係性が職場での満足度を大きく左右するという指摘も鋭いと感じました。
就職活動中に「会社選びで最も重要なのは直属の上司」というアドバイスを受けたというエピソードは、多くの社会人が経験を通じて実感することでしょう。
新たな視点
筆者が提案する「たたき台」としての資料作成アプローチは、私にとって新たな視点でした。
完璧を目指すよりも、上司の思考を整理するためのツールとして機能させるという考え方は、特に「ビジュアル思考が強く、具体的に形になったものを見ないと判断できない」タイプの上司に対して有効だと感じました。
現実的なアドバイス
この記事の素晴らしい点は、理想論ではなく現実に即したアドバイスを提供していることです。
非正規雇用の不安定さを認めつつも、その中でいかに精神的健康を保ち、キャリアを構築していくかという視点は非常に実用的です。
特に以下の具体的なアプローチ方法は、すぐに実践できる点で価値があります。
- 骨組みだけの資料を素早く作成する
- 小さな段階ごとに確認を取りながら進める
- 変更指示には素直に従う
- 完成したらすぐに確認してもらう
セルフケアの重要性
記事の後半で触れられているセルフケアの重要性も、働く人すべてに当てはまる貴重なアドバイスです。
仕事とプライベートの境界線を設けること、小さな達成感を大切にすること、職場以外の人間関係を育むこと、そして身体的なケアを怠らないことは、長期的なキャリアを考える上で欠かせない視点だと感じました。
総評
この記事は、非正規雇用という不安定な立場で働く方々のみならず、多くのビジネスパーソンに示唆に富む内容となっています。
「エネルギー配分の哲学」という考え方は、職場でのストレス軽減だけでなく、持続可能なキャリア構築や人生設計にも応用できる概念だと思いました。
DigitalAsuka28さんの経験から生まれた知恵と洞察に感謝します。
これからも現場からの声を発信し続けていただければと思います。
多くの読者が、この記事を通じて自分なりの「心の安定」を保つコツを見つける一助になることでしょう。